新年度になって異動しました.新しい学校は,武雄市立北方小学校で,またまた理科専科ということで理科の指導を行います.ありがたいことです(^^;)
さて,前回の書き込みから約1ヶ月になろうとしていますが,肝心の論文で示した教師の発話について知っておいたほうがよい知見があります.今回はこのことについて紹介します.
まずはじめは,『教師は児童・生徒が持っているであろうと考えられるスキーマを考慮した発話を行うことで,児童の概念形成や誤概念の修正に一定の効果を確認した』,ということです.
どういうことかと言えば,過去に教授した内容や与えた知識を児童らが参照できるような発話を行うと,概念形成に有利だと言うことになります.当たり前と言えばそうですが,このことを意識するかしないかでは大きな違いがあります.
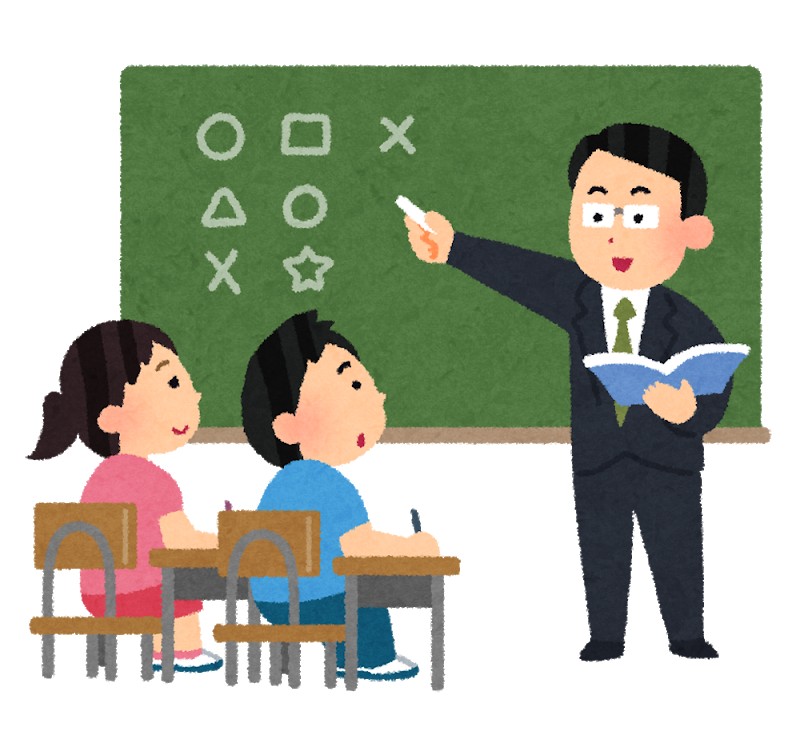
具体例で見ていきましょう.
前の時間に学習した内容を想起させるとき,「前回の授業で何を学びましたか」と質問するのはどうでしょうか.実は,これはNGです.NGというよりも,児童に対してはほとんど功を奏しません.
それよりも,例えば次のように発話すると,授業が盛り上がり想起する児童が一気に増えます.それは,「前回の授業で(ここまでは一緒です),このあたりに何かを書きましたよね」と言って,前回の授業のまとめを書いた黒板の領域辺りを手で示すのです.まとめを書いた領域の形に沿って手を動かすと効果的です.そのときに,まとめを行うときに起こったエピソード(例えば,児童の誰かの発言をもとにまとめたなど)も紹介すると,児童は想起できます.つまり,そのときのエピソード記憶に関係した言語を発話するようにすればいいのです.
例①「前回の授業では,〇〇の考え方に近い方法で問題を解きましたね」←〇〇が想起するための手がかり.
例②「この形を見ると何か思い出しますね」←前回に使用したある特徴的な形をジェスチャーで示したり,板書したりする.
例③「〇〇さんの方法で解けたよね」←〇〇がチャンクとなりますので,前回の授業では,〇〇さん方式などでまとめておけば,想起が楽に行なえます.そのためには,授業の折に,後で使えるエピソードを仕掛けておくこともありですね.
今回はここまでです.お読みいただきありがとうございました.